未来へと紡がれし
言ノ葉。
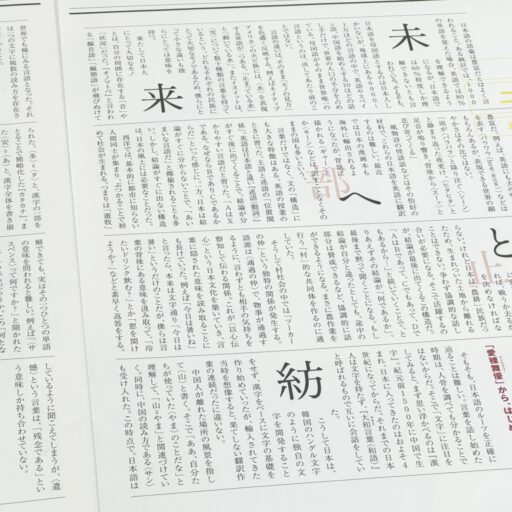
初出はGENERATION TIMES vol.8(2007年4月発行)に掲載。「日本らしさとは何か?」を特集テーマにした号で、改めて「日本語」についての特徴を取材しまとめた記事にです。世界から言葉が失われていく現代社会の中で、「日本人としての独自言語がある」というのは、とても貴重なことだと思い出します。
『もったいない』。この言葉は、今や「地球環境」を考えるときのキャッチフレーズになった。もとを辿れば、ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイさんが2005年に来日した際、「『Reduce(減らす)』『Recycle(再資源化)』『Reuse(再使用)』と、3つの単語で表してきた環境問題のメッセージを、たったひと言で表現できている」と感銘を受けて、世界中に再認識された言葉。
「翻訳できない日本語」=「独自の日本文化」。日本語には、僕ら日本人がまだまだ気づいていない文化を紐解く〈鍵〉が数多く隠されているのかもしれない。
文:伊藤剛
取材協力:加賀野井秀一(中央大学教授 言語学・哲学・メディア論)
日本語の語彙は豊富だとはよく言われること。ある統計では、1000の単語を覚えた場合、英語では80%を理解できるようになるが、日本語では60%程度しか理解できないとも言われている。そもそも、日本語を母国語とするのは日本人しかいないが、地球上にある6000~1万ほどの言語の中で、英語やスペイン語、中国語を始めとする10ほどの話し手だけで、世界の人口の半分を占めている。母国語がそのまま世界唯一の言語というのは、決してあたり前のことではない。
言語の違いは、そのまま「モノの見方」を色濃く反映する。例えばネイティブアメリカンのホピ族には、〈水〉を表現する単語が二つある。「止まっている水」と「動いている水」。またイヌイットは、〈雪〉について数十種類の言葉を持っているという。どれもそれぞれの民族にとって大切なモノであるため、僕らにとって小さな違いも彼らにとっては意味を持つ。
果たして日本人にとって大切なモノとは、自分の周囲に存在する「音」や「状況」だった。『オノマトペ』と言われる「擬音語」「擬態語」が飛びぬけて豊富だ。例えば、英語にも犬の鳴き声を表す〈バウワウ(bow-wow)〉などはもちろんあるが、表現できる世界の細やかさはその比ではない。
雨が〈パラパラ〉と降り注ぐ〈シーン〉と静まり返った夜更け、〈ヒタヒタ〉と足音が鳴り響き、背後から〈スーッ〉と忍び寄ってくる。
風物詩の怪談話などはその恰好の材料で、これらの日本語を英語に翻訳するのは難しい。最近では日本の漫画本も、海外に輸出されるようになったが、背景に描かれる〈ギャー〉とか〈キーン〉などは、訳すことなくそのままの国も多いという。
言葉だけではなく、文の「構造」にも大きな特徴はある。英語の授業のときに習った、主語と述語の「位置関係」。英語は日本語と違い『述語(動詞)』がすぐ後に出てくることで、結論が分かりやすい言語だと習った。「AはXである。なぜならBでありCであるからだ」といった感じに。一方、日本は結論がすぐに分からないことで、「あいまいな言語だ」と揶揄されることも多い。しかし、結論がすぐに出ない構造は、日本の風土には必要なことだった。
西洋では、基本的に都市に知らない人間同士が集まり、ぶつかることで初めて社会が生まれる。つまりは「遊牧」民族。自分の意思は即座に告げ、互いに意見が合わなければ、戦うか去るかを決めなければならない。けれど日本は「農耕」民族だったため、生まれついた土地から離れることはできない。争わず協調的な話し合いが必要になる。そこで活躍するのが、結論が最後に出てくるこの構造だ。
「AはBであって、Cでもあって、Dでもあるから…」と続いていくことで、とりあえずその結論が「何であるか」、最後まで黙って聞くことになる。もし結論が自分と違ったとしても、途中の部分は賛成できるなど、協調的に話ができるようになる。まさに農作業を行う「村」的な共同体を作るのに適していた。
そうして村社会の中では「ツーカーの仲」という独特の関係が発生する。語源は〈通過の仲〉で、物事が通過するように、言わずとも相手の気持ちを察知して伝わる関係。これが〈以心伝心〉という日本文化を築いていき、言葉に隠された意味を読み取ることにも長けていった。例えば「今日は暑いね」と言ったら、本来は文字通り「今日は暑い」というだけのことだが、僕らは言葉の背後にある意味を汲み取って、「冷たいドリンク飲む?」とか「窓を開けようか?」などと素早く返答をする。物事を荒立てずに済ませようとする〈事勿れ主義〉にもなりうるけれど、これは紛れもなく、日本人のひとつの能力である。
「愛裸舞優」から、はじめよう。
そもそも、日本語のルーツを正確に辿ることは難しい。言葉を話し始めた時期は、人骨を調べても分かることではないからだ。そこで「文字」に注目をしてみると、まず思い浮かべるのは『漢字』。紀元前1500年に中国で生まれ、日本に入ってきたのはおよそ4世紀になってからだ。それまでの日本人は文字を持たず、『大和言葉(和語)』と呼ばれるもので互いに会話をしていた。
こうして日本は、韓国のハングル文字のように独自の文字を開発することをせず、漢字をベースに文字の基礎を作り始めていったが、輸入されてきた当時を想像すると、果てしない翻訳作業の連続だったに違いない。
中国人が離れた場所の風景を指して〈山〉と書く。そこで「ああ、自分たちが使っていた〈やま〉のことだな」と理解して、「山=やま」と関連づけていく。同時に、中国の読み方である〈サン〉も受け入れた。この時点で、日本語は世界でも稀にみる言語となった。それは一つの文字に複数の読み方を存在させたということ。
例えば、〈行火〉という日本語。「ギョウ」なのか「コウ」なのか一文字目を迷った挙句、正解は「アンカ」と知って混乱する。地名も難しいものは多い。栃木県にある地名の〈四十八願〉。読み方は「ヨイナラ」。人名ともなるとさらに複雑で、名前の読み間違いは現在でも頻繁に起こる。ワープロの文字変換で、いくつもの選択肢が示されるのにもそれが端的に表れている。アルファベットの場合は、意味を知らない単語であったとしても、おおよその“発音”の見当をつけるくらいのことはできる。
こうした流れのなか、日本にしか存在しないモノを表現するために、漢字の意味を一切捨て去り、「音」として文字を使用する『万葉仮名』が登場した。一例を挙げると、〈夜麻(やま)〉〈可波(かわ)〉〈由岐(ゆき)〉〈伊呂(いろ)〉など。この発想はまさに現代にも受け継がれている『当て字』の類で、道の壁に書かれた〈夜露死苦(よろしく)〉〈愛裸舞優(あいらぶゆう)〉〈神出麗羅(しんでれら)〉などは、こうして考えてみると立派な万葉仮名である。
奈良時代の先人は、さらにウイットに富んだ遊び心を持っていた。万葉仮名の『戯書(ぎしょ)』と呼ばれる方法は、文字遊びの要素を取り込んだもの。例えば、〈二八十一〉で「にくく」と読み、〈重二〉で「し」と読ませた。これは「八十一=9×9(くく)」「2の二乗=4(し)」という数字の遊び。また、南の向かいの山〈向南山〉と書いて「きたやま」というようなものまである。先人たちの言葉のセンスもなかなかのものだ。
万葉仮名を巧みに使いこなしてきた日本人。けれど、一音ずつを漢字に変換するにはあまりに手間がかかることから、その省略を図ることが求められた。〈多〉=〈タ〉と、漢字の一部をとることで簡略化した『カタカナ』。また〈安〉=〈あ〉と、漢字全体を書き崩すことで『ひらがな』を生み出した。
こうして3つの文字のバリエーションを整えていった日本語だが、やがて漢字以来となる大きな変革期が訪れる。ときは鎖国を終え、西洋文化が大量に輸入された明治維新。日本語には全く存在しなかったあらゆる「モノ」と「思想」を、必死の思いで翻訳する作業に追われることとなった。
〈洋服〉もなければ〈国家〉という概念もない。〈国民〉〈社会〉〈地球〉〈恋愛〉〈法律〉〈自然〉〈世界〉〈人生〉…。どれもこの当時に作られた新造語である。それまでは、〈世界〉という単語があっても「よのなか」という意味であったし、〈自然〉も「ひとりでに」という意味で、現在の「ネイチャー」という意味になったのは、あくまで近代になってからだ。こうして、一万語ほどの新造語が生み出されることになった。
ノリと、気分と、フィーリング。
日本語は、漢字、西洋語という他言語の輸入に成功した稀な言語。それを可能にしたのは、『二重構造』と言われる特徴があったからだ。基本的に日本語は、名詞や形容詞などの『詞(自立語)』と、〈テニヲハ〉などの『辞(付属語)』という構造になっている。これがまさによくできた「翻訳装置」で、どんなに新しく入ってきた漢語やカタカナ語でも、『詞』の部分に〈テニヲハ〉さえくっつけておけば、一応は日本語に翻訳できているような気がするというもの。例えば、
「ちょい不良オヤジのセレブなゴージャスライフ」
「この映画はスリルとサスペンスに溢れている」
「若年層のニート現象は、失われた世代の象徴だ」
どれも昨今の雑誌の中に見受けられるような文章だが、感覚的には理解できても、実はその一つひとつの単語の意味を問われると難しい。例えば「〈サスペンス〉って何ですか?」と聞かれたら答えられるだろうか。この「何となく」という状態のまま、フィーリングで理解し話すことができてしまうのが、日本語の最も奇妙な特徴とも言える。西洋では、宗教と哲学の影響もあり、一つひとつの「言葉の定義」に長い年月を費やし、語源を正確に辞典に定めている。
〈神〉とは何であるか。〈命〉とは何であるか。互いに誤解があっては思想の統一はできない。〈サスペンス〉の場合も、非常に論理的に説明することができる。ズボンを吊り上げるものは〈サスペンダー〉。車の車輪を浮かせているものは〈サスペンション〉。つまり〈サスペンス〉とは、「心を宙吊りにさせるような状態のこと」となる。
こう考えていくと「これぞ日本語だ」と思っているものでさえ、あやふやだということに気付く。「ゆとり教育」の〈ゆとり〉って何? 「天皇は神聖な存在」の〈神聖〉って何? あらゆる言葉の定義があいまいだ。だからこそ、発する音の「感覚」や、漢字の見栄えから受ける「印象」が、日本人にとっての重要度を占めることになり、それは『言霊』思想にも繋がっている。おそらく日本人が初めて出合った文字が、漢字という「ビジュアル」なものであったことが原体験となっているのだろう。この言語の特性が、僕らの知らぬ間に権力者によって騙されてしまう土壌を作っている。
第二次世界大戦中、日本軍の戦況を伝えるために言葉の置き換えが行われていた。他国の目を意識して〈侵略〉ではなく〈進出〉という言葉を使い、自軍の〈全滅〉を〈玉砕〉に置き換え、〈敗戦〉を〈終戦〉と呼んだ。現在でも、〈軍隊〉ではなく〈自衛隊〉と言い換えることで問題をあいまいにする。テレビでたびたび耳にする「これは〈遺憾〉の念である」という表現。これも謝罪しているように聞こえてしまうが、〈遺憾〉という言葉は、「残念である」という意味しか持ち合わせていない。
言葉は未来へと紡がれて
言語学者のソシュール(※1)は、言葉についてこう語った。「言語こそが世界に切れ目を入れて、名前を名づけることで、初めてそのものを存在させる」。つまり、言語は「関係性」から成り立っているということ。そして関係性と言えば、こんな側面も興味深いエピソードだ。
時々話題に上る日本の捕鯨問題。〈鯨〉は、生物学上「哺乳類」に分類されているが、日本語ではその言葉に〈魚〉偏を使っていることに、先人たちが発見した「関係」を垣間見ることができる。
数千年の歴史を持つ日本語。言葉を増やしながら、知覚できる世界を少しずつ広げてきた。これらの言葉は、僕らの先人たちが長い年月をかけて、生まれ育ったこの土地で見つけた「関係」のすべて。つまり、僕らは彼らが「発見した世界」の中で生きているということだ。だから、日本語を話せば話すほど、先人の思考が僕らの行動様式を作っていく。
「いま」話している言葉もいつかは古くなり、新しい言葉に置き換わりながら姿を変えていく。そうして、また一千年先の日本人もこの言葉を話していたとしたら、それは僕らが受け継ぎ、発見し積み重ねた、新しい日本の姿だ。
参考文献
『あたらしい教科書 ことば』(ブチグラパブリッシング)監修:加賀野井秀一、酒井邦嘉、竹内敏晴、橋爪大三郎
『日本語は進化する』(NHKブックス)著:加賀野井秀一
『日本語の歴史』(岩波新書)著:山口仲美
『日本語から日本が見える』(東京新聞出版局)著:倉島長正
『日本語の本質』(文春文庫)著:司馬遼太郎




