ABOUT
ミンナデ タノシク アソボット
はじめまして、アソボットです。「伝えたいコトを、伝わるカタチに」をコンセプトに、「世の中とのかかわり方」をつくるコミュニケーション・デザインの会社です。
メディアの編集者や、広告PRを専門とするメンバーが集い、雑誌や書籍、WEBサイトやミュージアムなどさまざまなコンテンツを制作したり、いろいろな企業やNPOなどのブランディングやコミュニケーション戦略を策定するお手伝いをしています。
「伝える」と「伝わる」。日本語では “たった一文字” の違いですが、そのふたつは大きく異なります。「伝えているけれど、伝わらない」。そういうことが、世の中にはたくさん存在しています。だからか、“伝え方の技法”に関心が向きがちですが、もっとも重要なことは、伝えたい相手が「誰」なのかを認識して、その「伝わり方」から考えること。つまり、“コミュニケーションする”ということです。
そんな私たちがずっと大切にしてきたことは、「世の中」と誠実に向き合うことです。そこには、いわゆる「社会イシュー」と呼ばれるものがあります。 ジェンダーや少子高齢社会、感染症や自然災害、戦争や人権など、どれもあまりに大きな問題で、できれば目を逸らしたくなりますが、私たちの暮らしや次世代に影響を与える、決して無視のできないことです。だからこそ、それらを身近に考えるためのコンテンツ作りや、課題解決をする団体や活動を支えていきたいと思っています。
一方で、私たちは「大きな問題」ばかりを考えて、日々暮らしていくことはできません。おいしい食事や胸おどる映画や音楽、手に汗握るスポーツ観戦。非常時には“不要不急”と切り捨てられてしまいがちな「文化」や「カルチャー」を丁寧に育んでいくことも、私たちの社会にとって大切なことだと考えています。
このように、アソボットの仕事というのは、社会的・文化的の両面から「伝える」と「伝わる」の間をいろいろなアイデアで埋めていくこと。たとえば、企業と生活者の、地域と市民の、世界と自分の、そんな関係性にある“隔たり”です。
HPには、会社としての壮大なビジョンやパーパスを掲げていませんが、目指したい行き先は“ひとり”では決して辿り着けない場所です。だから、「ミンナデ タノシク アソボット」。どうぞ、よろしくお願いいたします。



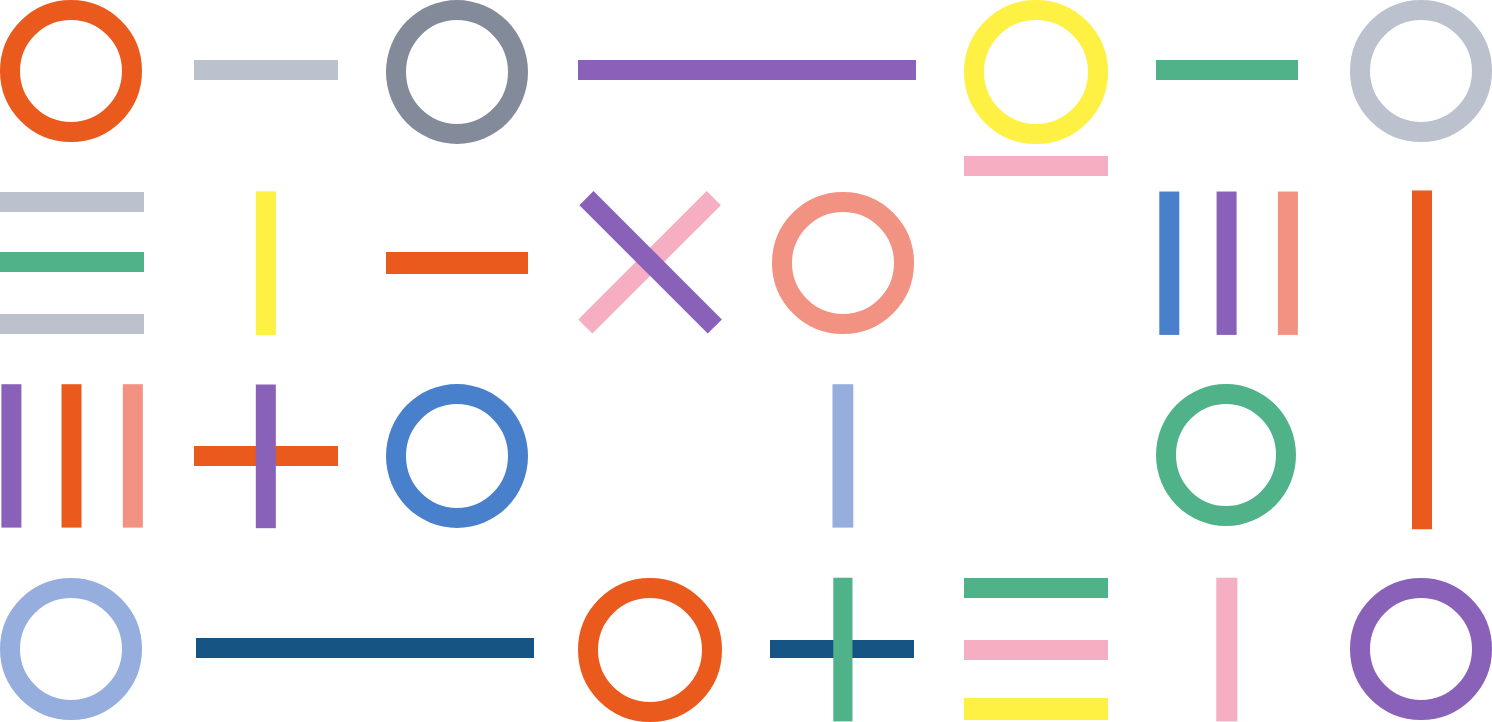
「伝える」と「伝わる」は違う
創業以来、アソボットは「コミュニケーションとは何か」について考え続けてきました。 どうしたら伝わるのか。なぜ伝わらないのか。そんな疑問を抱き続けていたのには、常に私たちの中に「伝えたいコト」があったからでもあります。
今でも「正解を導く公式」は見つかっていません。コミュニケーションが、人と人との間にある以上、なかなか正解はありません。それでも、自分たちなりの「考え方」はあります。哲学とまではいえない、アソボットの「プチ哲学」のようなものです。
<コミュニケーションと「インフォメーション」はどう違う?><思考の出発点【A】の正体は?><コトバとイメージの密接な関係>など、9つのTipsにまとめてみました。順番に読み進めていただくことで、コミュニケーションとは何かが、ほんの少し「伝わる」かもしれません。
「恋愛」から「戦争」まで
同じテーブルの上に乗せる
2001年に創業してから、アソボットはいろいろな人たちの「伝えたいコト」を、さまざまな「伝わるカタチ」にしてきました。関わってきた分野や領域も、カジュアルなものから真面目なものまでありますが、私たちはその「幅」こそが大切だと思っています。
一見、両極端に見える「恋愛」や「戦争」のようなテーマであっても、丁寧に紐解けばそれらは「人と人の営み方」に関わることです。たとえば、被災地に必要な支援が、食糧や住居だけでなく、文化や娯楽、時には“一輪の花”が必要とされるように、社会性も文化的なことも、どちらもこの世の中が豊かであるために決して切り離せないことだと、私たちは考えています。
これらは創業20周年の際にまとめた、2001年から2020年までの「伝えたいコトを、伝わるカタチ」にした事例集になります。どうぞご覧ください。
仕事のご相談や、
JOURNALの企画についてなど
まずはお気軽にお問い合わせください。



